市内河川の水質検査結果
市では、市内の主な河川7ヵ所の水質検査(生活環境項目:5項目)を毎年4回実施しています。
採水場所
- 鉄山川(下久保原橋)
- 二十里川(二十里橋)
- 池島川(池島橋)
- 長江川(長江川橋)
- 関川(関川橋)
- 西境川(新岩次橋)
- 白川(山川橋)
河川水質検査位置図
環境基準
環境基本法に基づく水質に係る環境基準は、水質保全行政の目標として公共用水域の水質について達成し、維持されることが望ましい基準を定めたものであり、人の健康の保護に関するものと生活環境の保全に関するものがあります。
生活環境の保全に関するものについて、河川ごとに水域類型に基準値を定めており、各公共用水域について水域類型の指定が行われています。
川内川(川内川に流入する河川も含む)の環境基準は、河川A類型に指定されています。
分析項目(用語解説)
水素イオン濃度 pH(ペーハー)
水の酸性・アルカリ性を示すもので、pHが7のときは中性、これより数値の高い場合はアルカリ性、低い場合は酸性であることを示します。生活排水、工場排水などの人為汚染、夏期における植物プランクトンの光合成などの要因によりpHが急激に変化することがあります。
生物化学的酸素要求量 BOD(ビーオーディー)
水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素の量で、河川水質の代表的な指標の一つになっています。
BODが高いとDO(溶存酸素)が欠乏しやすくなり、1リットル当たり10ミリグラム以上で悪臭の発生などがみられます。
浮遊物質量 SS(エスエス)
水中に懸濁している不溶解性の粒子状物質のことで、粘土鉱物に由来する微粒子や動植物プランクトン及びその死骸、下水・工場排水などに由来する有機物や金属の沈殿などが含まれます。高濃度では、魚の呼吸障害、水中植物の光合成妨害や沈殿物として底質への影響があります。
通常の河川のSS(エスエス)は、25~100ミリグラム/L以下ですが、降雨後の濁水の流出時には1リットルあたり数百ミリグラム以上になることもあります。
溶存酸素 DO(ディーオー)
水中に溶解している酸素量を言い、有機物による汚染の目立つほど低い濃度となります。
酸素は、河川や海域の自浄作用、魚類などの水生生物には不可欠であり、溶存酸素が低下すると好気性微生物の活動を抑制することになり浄化作用が低下し、水生生物の窒息死を招きます。
大腸菌数
大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出され、水のふん便汚染の指標として使われる数値です。大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位:Colony Forming Unit)/100ミリリットルで、値が小さいほどヒトや動物からの排泄物による汚染が少ないと言えます。
令和4年3月31日までは大腸菌群数が指標になっていました。大腸菌群とは、大腸菌および大腸菌ときわめてよく似た性質を持つ細菌の総称です。水環境中において大腸菌群が多く検出されても、大腸菌が検出されない場合があり、大腸菌群数がふん便汚染を的確に捉えていない状況がみられたため、環境基準の値も大腸菌群数から大腸菌数に見直されています。
水質検査結果
令和元・2年度水質検査結果 (PDFファイル: 71.9KB)
令和3・4年度水質検査結果 (PDFファイル: 72.5KB)
水環境を守るために
水質悪化の要因には、皆さんが生活で使用する台所、風呂などの生活雑排水や事業場、畜舎、農地等からの排水が考えられます。将来の水環境を守るために、一人一人の排水に対する心掛けが大切です。
私たちが共有する貴重な財産でもある河川を魚類の生息しやすい環境にしていきましょう。
家庭でできる生活排水対策
- 食器や鍋の油は、拭き取ってから洗いましょう
- 野菜くず、残飯などは台所で回収しましょう
- 洗剤は、使いすぎないようにしましょう。








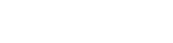
更新日:2025年03月21日