介護保険制度の概要
介護保険制度
介護保険制度制定の趣旨
私たちは今、高齢社会の中にあり、21世紀半ばには3人に1人が65歳以上という時代を迎えようとしています。この高齢社会において、寝たきりや認知症などにより介護を必要とする人が急速に増加し、介護の問題は老後生活における最大の不安要因となっています。
介護の問題は、自らが介護を必要とする状態になったり、または介護を必要とする状態となった親を持ったりするなど、今後誰もが直面する問題になっています。
そこで、介護を必要とする人を社会全体で支える新しい制度として「介護保険制度」が創設されました。
介護保険制度が平成12年から施行されて以来、3年に1度制度の改正が行われます。
介護保険制度の運営は?
介護保険制度はえびの市が保険者となって運営をしています。
どういった人が加入するの?
原則40歳以上の人が介護保険の被保険者となり、年齢などにより次のように区分されます。
- 第1号被保険者:65歳以上の人
- 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の人で医療保険に加入されている人
介護保険の財源は?
介護保険の財源は以下のグラフのようになります。介護サービスを利用した際の利用者負担は1割となっていましたが、一定以上の所得がある第1号被保険者(65歳以上)の利用者負担は、2割(平成27年8月実施)となりました。また、2割負担のうち特に所得の高い人の負担が3割負担(平成30年8月実施)となります。
被保険者の保険料と国・県・市の公費でそれぞれ半分ずつ負担して制度を運営するための大切な財源とします。

現役並みの所得のある人の利用負担の見直し(平成30年8月実施)
| 要件 | 利用者負担 |
|---|---|
| 合計所得が160万円未満の人 | 1割負担 |
| 合計所得が160万円以上220万円未満で且つ、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得を合せた金額が単身世帯で280万円未満の人、2人以上の世帯で346万円未満の人 | 1割負担 |
| 合計所得が160万円以上220万円未満で且つ、上記以外の人 | 2割負担 |
| 合計所得が220万円以上で且つ、年金収入とその他の合計所得を合わせた金額が340万円以上の人、2人以上の世帯で463万円以上の人 | 3割負担 |
(注釈)その他の合計所得金額とは、給与収入や事業収入から給与所得控除や必要経費を控除した金額です。
介護保険料
第1号被保険者
介護保険料の決め方
えびの市で必要とする介護サービスの総費用のうち、第1号被保険者負担分(23%)を65歳以上の人数で割って基準額を算出します。第9期(令和6年度から令和8年度)の第1号介護保険料は、所得水準に応じてきめ細やかな保険料設定を行うため標準段階を13段階とし、この基準額をもとに保険料額が決められます。また、国では、低所得者に対して公費を投入して、第1号介護保険料の負担軽減を行う仕組みを引き続き設けることにしています。
令和6年度から令和8年度の保険料
| 所得段階 | 対象者 | 年額 | 標準割合 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護被保護者、世帯全員が市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者、世帯全員が非課税かつ本人年金収入等809,000円以下の人 | 21,204円 | 基準額×0.285 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税かつ本人年金収入等809,000円超120万円以下の人 | 36,084円 | 基準額×0.485 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税でかつ本人年金収入等120万円超の人 | 50,964円 | 基準額×0.685 |
| 第4段階 | 本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等809,000円以下の人 | 66,960円 | 基準額×0.90 |
| 第5段階 | 本人が市民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等809,000円超の人 | 74,400円 | 基準額 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 89,280円 | 基準額×1.20 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 96,720円 | 基準額×1.30 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 111,600円 | 基準額×1.50 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 126,480円 | 基準額×1.70 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 141,360円 | 基準額×1.90 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 156,240円 | 基準額×2.10 |
| 第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 171,120円 | 基準額×2.30 |
| 第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上の人 | 178,560円 | 基準額×2.40 |
(注意)所得段階は、本人および世帯の申告内容に基づき毎年見直しが行われます。
第1号介護保険料の公費による保険料軽減強化
第1段階について、保険料基準額に対する割合を、0.285に軽減する。 第2段階について、保険料基準額に対する割合を、0.485に軽減する。 第3段階について、保険料基準額に対する割合を、0.685に軽減する。
介護保険料の納付方法等
介護保険料は原則として特別徴収(年金からの差し引き)が優先されますが、年金の額によっては、普通徴収(納付書または口座振替)で納めます。
また、次のような場合には、しばらくの間「普通徴収」になります。
- 65歳に到達された人
- 他の市町村から転入された人
- 現況届の出し忘れなど、特別の理由により年金の支給が停止したとき
- 保険料の所得段階が変わり、年度途中で当該年度の保険料を完納したとき
| 年金の受給額 | 年金の種類 | 納め方 | 徴収方法 |
|---|---|---|---|
| 年額18万円以上 | 老齢基礎年金など | 受給している年金から介護保険料があらかじめ差し引かれます。 | 特別徴収 |
| 年額18万円未満 | 市役所から送付される納付書により、介護保険料を納付してもらいます。 口座振替の利用もできます。 |
普通徴収 |
第2号被保険者
介護保険料の決め方・納付方法
第2号被保険者の人の介護保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められ医療保険料と一括して納めます。
保険料の算定方法等について
| 国民健康保険 | 職場の医療保険 | |
|---|---|---|
| 算定方法 | 所得や資産等に応じて世帯ごとに算定されます。 | 加入している医療保険の算定方法により決まります。 |
| 負担 | 原則として、本人が2分の1、国が2分の1を負担します。 | 原則として、本人が2分の1、事業主が2分の1を負担します。 |
| 納付方法 | 医療分と介護分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納付します。 | 医療分と介護分をあわせて健康保険料として給料から差し引かれます。 |
第2号被保険者に対する介護保険制度リーフレット (PDFファイル: 354.0KB)
介護サービスの利用
介護サービスを利用するには…
介護保険のサービスを受けるためには、要介護認定などの申請をし、寝たきりや認知症などで介護が必要な状態かどうかの認定(要介護認定)を受ける必要があります。
要介護認定の申請からサービス利用まで
- 利用者
- 要介護等認定申請
申請は本人や家族のほか、近くの居宅介護支援事業者や介護保険施設(更新・申請・区分変更に限る)にも代行を依頼することができます。
- 要介護等認定申請
- 市町村
- 訪問調査の実施
市役所の職員や市から委託を受けた居宅介護支援事業者の介護支援専門員が家庭などを訪問し、申請者の心身の状態を調査します。 - 意見書の作成依頼
主治医に意見書の作成を依頼します。 - 一次判定の実施
訪問調査の結果と意見書の内容に基づきコンピュータ判定を行います。
- 訪問調査の実施
- 介護認定審査会
- 審査判定
一次判定の結果と主治医の意見書をもとに、介護が必要かどうかを医師や保健・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、7ランクにわけて判定します。
- 審査判定
- 市町村
- 認定
介護認定審査会の判定結果に基づいて市町村が認定し、その結果を申請者に通知します。
- 認定
- 利用者
- 居宅介護サービス計画の作成依頼
介護が必要と認定されたら、どのようなサービスを受けたらよいか、介護支援専門員と相談しながら介護サービスの計画を作成しサービスの利用を開始します。
- 居宅介護サービス計画の作成依頼
- サービスの利用
介護保険で利用できるサービス
介護保険では、認定を受けた人はどなたでも利用できる在宅サービスと、要介護1以上の認定を受けた人が利用できる施設サービスがあります。
(注意)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への新規入所は、原則、要介護3以上の人となります。
在宅サービス
| 家庭を訪問するサービス | 訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・訪問入浴介護・居宅療養管理指導 |
|---|---|
| 日帰りで通うサービス | 通所介護・地域密着型通所介護・通所リハビリテーション |
| 施設への短期入所サービス | 短期入所生活介護・短期入所療養介護 |
| 福祉用具の貸与・購入や住宅の改修 | 福祉用具の貸与・福祉用具購入費の支給・住宅改修費の支給 |
施設サービス
サービスの種類
- 介護老人福祉施設サービス
- 介護老人保健施設サービス
特別養護老人ホームへの新規入所者の中重度化(平成27年4月実施)
特別養護老人ホームへの新規入所者を原則として要介護3以上の要介護者に限定します。要介護1・2の人は、在宅で日常生活を営むことが困難であるなどのやむを得ない事由があると認められた場合に、特例入所として申し込みができます。
費用の1割または、2割・3割は、利用者の負担です
サービス利用者の負担
介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担します。ただし、平成27年8月から一定以上所得者の人は、費用の2割を負担します。また、平成30年8月から制度改正により2割負担のうち特に所得の高い人の負担が3割となります。施設に入所した場合は、費用の1割または2割・3割のほかに、食費と居住費(短期入所の場合は滞在費)もあわせて負担することになります。
高額な費用負担について
介護保険では、同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
1カ月あたりの利用者負担上限額
| 利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円 (年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
| 世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| 世帯の全員が市町村民税非課税であり 前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額 の合計が80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 生活保護を受給者している方等 | 15,000円(世帯) |
介護保険負担限度額認定について
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への助成(補足給付)を行っています。
(注意)補足給付は、世帯全員(別世帯の配偶者を含みます)が市町村民税非課税の場合が対象です。
預貯金の要件
第1段階
- 生活保護受給者
- 市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給
- 単身 1,000万円 夫婦 2,000万円
第2段階
- 市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と 【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の 合計額が年額80万円以下の方
(注釈)遺族年金は寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む。以下同じ。
- 単身 650万円 夫婦 1,650万円
第3段階(1)
- 市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と 【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の 合計額が年額80万円を超え、120万円以下の方
- 単身 550万円 夫婦 1,550万円
第3段階(2)
- 市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と 【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の 合計額が年額120万円超えの方
- 単身 500万円 夫婦 1,500万円
(注意)第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、1,000万円(夫婦は2,000万円)以下
1日あたりの負担限度額
第1段階
1.生活保護受給者
2.市町村民税世帯非課税である老齢福祉年金受給者
居住費
ユニット型個室:880円
ユニット型個室的多床室:550円
従来型個室:550円(380円)
多床室:0円
食費
施設入所者:300円
ショートステイ利用者:300円
第2段階
1.市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と 【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額80万円以下の方
(注釈)遺族年金は寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む。以下同じ。
居住費
ユニット型個室:880円
ユニット型個室的多床室:550円
従来型個室:550円(480円)
多床室:430円
食費
施設入所者:390円
ショートステイ利用者:600円
第3段階(1)
1.市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と 【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額80万円を超え、120万円以下の方
居住費
ユニット型個室:1,370円
ユニット型個室的多床室:1,370円
従来型個室:1,370円(880円)
多床室:430円
食費
施設入所者:650円
ショートステイ利用者: 1,000円
第3段階(2)
1.市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と 【遺族年金・障害年金】の収入額、その他の合計所得金額の合計額が年額120万円超えの方
居住費
ユニット型個室:1,370円
ユニット型個室的多床室:1,370円
従来型個室:1,370円(880円)
多床室:430円
食費
施設入所者:1,360円
ショートステイ利用者:1,300円
(注意)介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額が、()内の金額となります。
令和6年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに係るリーフレット(周知) (PDFファイル: 252.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
えびの市 介護保険課 介護保険係
郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地
電話番号:0984-48-0352
ファクス:0984-35-0401
お問い合わせはこちら








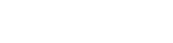
更新日:2025年04月01日